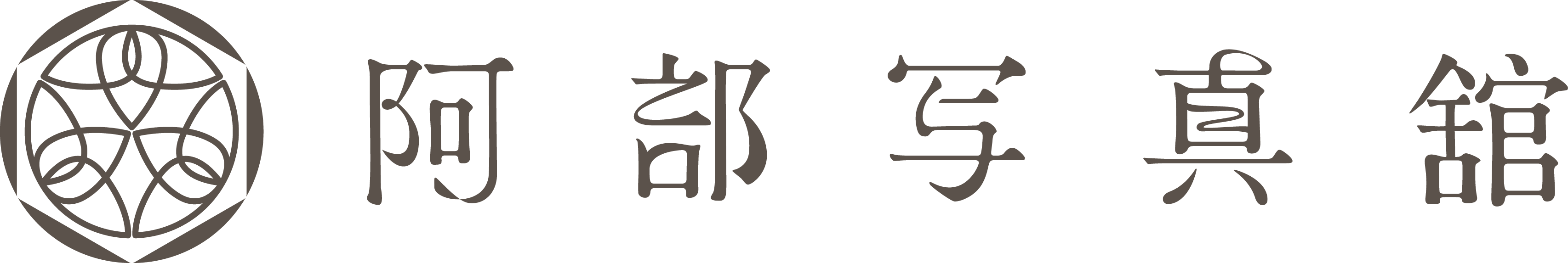これは書きかけの小説の冒頭です。
「喜作さん」
阿部浩之
まだ三歳に届かぬ浩は、先ほどから米糠でよく磨かれて黒光りする桜木の縁側によじ登ろうとするのだが、どうしても這い登ることができない。後ろで鶏が卵を産んでいる。叫びに似た鳴声が浩の背中を押しているようだ。いつもなら爺ちゃんが助けてくれるのだが、誰も見ていない。もし浩が滑り落ちたら青石を磨いた沓脱石で頭を打ち付けるかもしれない。
爺ちゃんは、さっきから店の玄関先でラビット・スクーターのエンジンをかけているのだが、なかなか始動しない。まだ働く職人さんたちの朝ごはんには早く、母さんも支度には間がある。いまは店先の掃き掃除で忙しい。
「ひろし! そこ危ないでー」
「爺ちゃん!助けてやってー」
母が叫ぶ。こんなこともあるので、厠と釜戸には幼児が入り込まないように柵をしてある。爺ちゃんは何かにつけて抜かりないが、スクーターをいじり出すと注意がおろそかになる。このスクーターでどこへ配達に行くのやら定かでないが、このところ出動が多い。
(いったい爺ちゃんはどこへ行くのだろう)
浩は幼い心のうちにも、不安がよぎる。
(僕も連れてって!)そう叫びたいのだ。
タタン、タンタンタン、タタン、タンタンタン
2サイクルラビットのエンジンは白い煙を吐きながらようやく立ち上がる。濛々と白い煙が立ち昇る。浩の父親はどこかの勤め人でいつも店には関心がない。朝早くにここを出て、帰りはいつも浩が寝静まってからだ。
爺ちゃんは時々男になるときがある。名前は喜作という。店でも「親方」などと呼ばれず、皆が「きさくさん」と呼んでいる。爺ちゃんは一通りの配達指示を丁稚たちに済ませると、タンタンタンとラビットのエンジン音を響かせてどこかへ出かけていく。これが最近は三日に一度になってきた。出かける前は異様なほど浩をかわいがるが、心は彼方へ向いている。今朝もその日なのだ。母はそれを心得ていて、自分も苛々しないよう気を配っているのだが、爺ちゃんから男の顔に戻っている素振りを母はいちばんに察知している。
喜作にはまだ中学生になったばかりの四男克也がいる。浩の父の末弟ということになる。克也を産んでしばらくして彼の母親は死んだ。脳溢血で突然旅立った。喜作は独り身に戻ったわけだ。浩の母にしてみれば爺ちゃんの子、克也を預かって余分な子育てをするようなもの。それをいいことに爺ちゃんは克也のことを忘れたかの様子で、かわいがることはなかった。もっぱら爺ちゃんは浩のことばかり気にかけていた。
その日はラビットに乗って出かけたきり喜作は帰らなかった。
深夜になって店の電話が鳴った。浩の耳にも届くほど、それは長い間鳴っていたが、母さんの電話の声が土間に響く。
「それで、あなたどうなさるの?」
寝床の浩にもわかるほど、少し沈んだ声の母。しばらくして電話は切られた。
「浩、起きてたんか。爺ちゃんが亡くなったんやって。死んだんよ」
そんなこと言われて浩にわかるはずもなかったが、母は誰かに話すことで自分の心の重しをわずかでも軽くしたかったのだろう。克也には何と言ったらいいのか。母には思いつかなかった。
ひろしの父が明け方名古屋から帰ってきた。母さんに何か話している。
「爺ちゃん、お妾さんの家で亡くなったんだ。後のことは段取りしてきたが、克也にどう説明するか?」
・・・(続く)

写真は喜作?と私
中途半端なショート・ショートにお付き合いいただき。ありがとうございました。これはフィクションです。
書き散らすのは得意だが、完成させたことのない自分が情けなくもある。