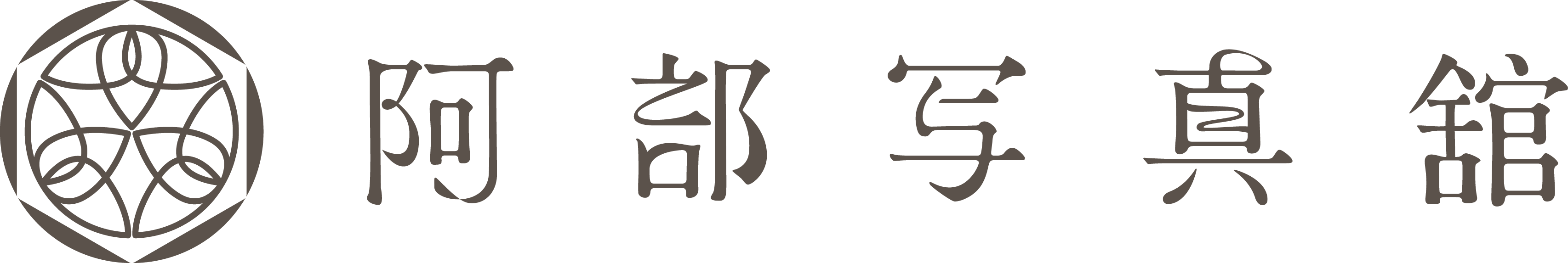書き散らしたままの未完小説を、いったいどうすればいいのか。意志薄弱な自分がいる。少しの時間おつきあいください。

東海道本線 垂水駅辺り
「1・9・7・0」
通行量も少なくなり諦めかけていると、二人の眼前を勢いよく通り過ぎた黒塗りのクラウン。バックしてきて路肩に停まった。二人は一瞬躊躇した。遠目に見ても怪しい車。
右側のドアが開く。片足だけを下ろしてこちらを振り返っている。運転手が手招きしている。芳雄と裕史は互いに見つめ合い、芳雄は裕史に聞いてくる。
「おい!どうする? 」
時間は深夜の2時。ヒッチハイクで米原を出発したのが夜の8時。あれから6時間も経つのにまだ拾ってくれた車は2台目。
裕史は芳雄と目を交わす。一瞬で開き直った二人は、あの怪しい黒塗りの車に乗せてもらうことにする。小走りに車のもとへ行くと、ドアが中から開けられた。後席に二人乗り込むと、かなり乱暴に 発進した。
走り出してすぐに気付く。どうも前席の二人の会話を聴いていると、運転しているのが親分。助手席には子分を乗せている。お前たちはどこへ行くのか。彼女はおらんのかと、通り一遍の会話を進めるうちに突然声が変わる。運転するアニキは太めの声で、
「わしは背中にゃ刀傷もあるんやで。お前らなんかこのまま、タコ部屋に売り渡せるんやで」
(おっと!) 脅してきた。
凍り付いた。二人はスピードを緩めたスキに逃げようと合図し合い、気付かれぬようドアノブを握る。意外と冷静さは失っていなかったが、手は汗ばんだ。声も上ずっていたに違いない。
あとでアニキは笑いながら、
「あれは冗談やった。ごめんごめん」
そう独り芝居を演じた後、お詫びに、
「メシ奢ったるわ」
深夜のドライブイン〈ルート21〉へ入る。兄貴はこの店によく立ち寄るらしい。かつ丼が旨かった。二人がガツガツ食べる姿をアニキは楽しそうに見つめていた。我々に本物の刀傷をみせて彼は自慢した。逢坂峠手前まで回り道して送ってくれた。
兄貴は「カネは大事やぞ」というのが口癖。何でも独力で突破するタイプと見た。
「どうせ大学行っても、お前ら〈安保反対〉なんて叫ぶんやろ。それよりな。わしらの仕事手伝わんか」
「いや、僕ら安保賛成ですよ。日本が好きですから」
裕史は言葉を初めて返した。
「お前ら、いいこと言うな。昔の日本知っとるか。母さんを一番に大切にしたんやぞ」
「知っとるか。わしの兄貴の世代は特攻行ったんぞ」
どうも口癖は(知っとるか)とみた。年齢は30代か。
今度は芳雄が言葉を返す。
「僕の叔父もそうです。フィリピンのピナツボ火山に突っ込みました」
「そうか。わしのボスもフィリピン残留者じゃ。ハンパでない、肝が据わっとるぞ」
高三の秋、中間テスト明けのある晩、芳雄と裕史は示し合わせて、
「大阪万博へ行こう」
そんな提案をするのはいつも芳雄だ。学校を引けるとそれぞれ自宅で寝ダメし、夜を待って行動開始。東海道線で米原へ向かった。線路わきを国道が走っているからだ。列車を降りると国道21号線に出る。なかなかトラックは止まってくれない。歩き疲れると交代でトラックに向かって手を挙げた。そうこうするうちに深夜。しかたなくふたり西に向かってトボトボ歩きだした。
アニキと別れたふたりは一時間ほど歩いただろう。10トン積みのトレーラーが乗せてくれた。ドライバーは50歳くらいか。機嫌がいいらしい。鼻歌交じりに、
「君ら高校生か。ウィスキー飲んでもいいぞ?」
キャビンに蛍光灯が灯る。琥珀色のボトルが運転席側のドアポケットから出てきた。
深夜のヒッチハイカーは、その素性もわからず危険もあるが、ドライバーにとっては格好の話し相手にもなる。
降ろされるとふたたび歩き出す。芳雄が後ろから呼びかける。
「おい、裕史1 さっきのトラックやばかったな。あれは運転しながらウィスキー吞んどるぞ」
この峠を越えれば京都だ。トレーラーと別れて芳雄とふたり、並ばず一定の距離を取りながら峠を目指して歩き出した。二人連れでは相手が警戒してなかなか車を停めようとしないからだ。1時間は歩いただろうか。時折止まってくれそうな深夜便のトラックを探すが、相手もこちらの様子を確かめているのか、停止しそうになるが停まってはくれない。仕方なく二人とも口元を絞ったズタ袋様の荷物を担ぎ、トボトボ国道の左側を歩いた。お腹もふくれていたため眠気が襲ってくる時間だ。
(しまった!)
裕史は車の走行音もあり、異変に気付くのが遅れた。
後ろを歩く芳雄があっという間に大人二人に取り押さえられた。さすが慣れたもので小脇を抱えられ宙づり状態の芳雄。裕史はなりふり構わず友達を捨て、一目散に駆け出した。
(冷たいやつだ)
芳雄は心内でそう叫んだに違いない。しかし裕史の行く手からも大人二人連れが走り寄ってくる。絶体絶命。あっという間に取り押さえられてしまった。予想もしていなかった。なんと本職の刑事。用意周到だ。すぐ後ろにはパトカーまで来ているではないか。ふたりは諦めておとなしく捕まるしかない。逆に裕史は安どの表情か、(ヤクザよりましだ)そう思っていたのか。
ふたりパトカーに押し込まれ派出所に連行されると、別々に尋問が始まる。こってり絞られた。
「とにかく朝一番の列車で帰れ」
「学校に連絡するのは止めたるわ」
ここでも脅された。笑うしかない。派出所で朝まで留め置かれ、いや保護され、最寄り駅までパトカーで送ってくれた。
パトカーを降りると、ここまで来たふたりの意地だ。上り電車でなく大阪に向かう列車を待った。芳雄は弱気になっていたが、こんなとき裕史はへこまないようだ。始発の普通列車を待ち京都に向かう。ここから京都までは知れた距離だ。
京都駅前からまたふたりは歩き出す。二条城前のベンチでズタ袋を枕に新聞紙を被って寝た。寒かったが眠気が勝った。お金もないし観光に来たわけでもない。
この十月終わりの旅は二人にとって、とても塩辛いものだった。大阪まではたどり着けなかったが、高校生二人、世間の厳しさと暖かさを同時に思い知るには十分な旅だった。飯を奢ってくれたアニキ。ウィスキー片手に大型トラックのハンドルを握るドライバー。そして刑事達。
今ごろ芳雄はどうしているだろう。裕史は刑事になった。