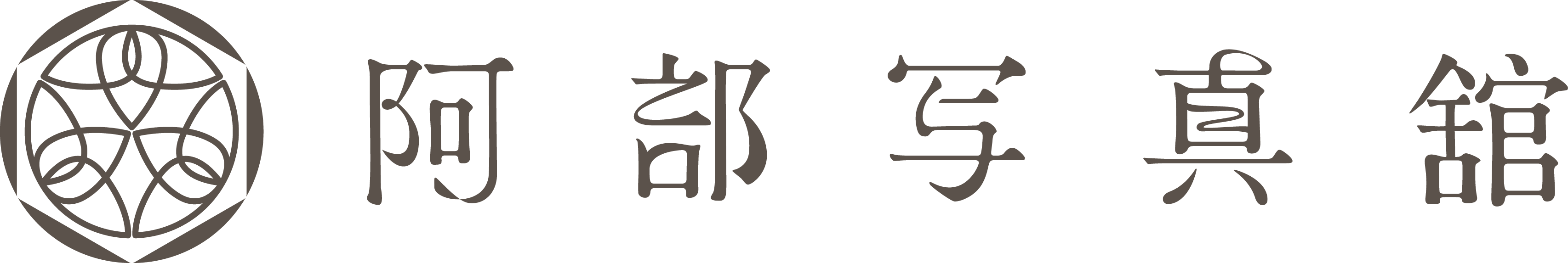過去には種田山頭火の自由律俳句をご紹介しましたが、今回の表題作、作者は尾崎放哉(1885~1926)です。
詠われたころの放哉は小豆島の小さな庵に独りきり。常人なら死を前にして悲嘆にくれている状況のはずだが、当の本人はそうではない。味わっているのだろう。自分が望んだことなのだから。
僕もこの気持ちが少しだけわかる年頃になった。
(買い被りかなあ?)
彼は今でいえば家族も捨て、人生そのものを崩壊させた世捨て人であり、許されざる行為を成したともいえるが、この独白にも似た俳句が、今の僕に美しく映えるのであるから仕方ない。「独り」というのが何とも切なくて、それでいて(なんともいいんだなあ)と思えてくるのだから。

このカットは山陰本線の島根県某駅の待合室で撮られた自分の姿。ガラス戸を開ければ雪が舞い込んでくる。なぜここにいるのか、なぜこんな写真を撮ったのか、本人もわからない。撮影は1976年