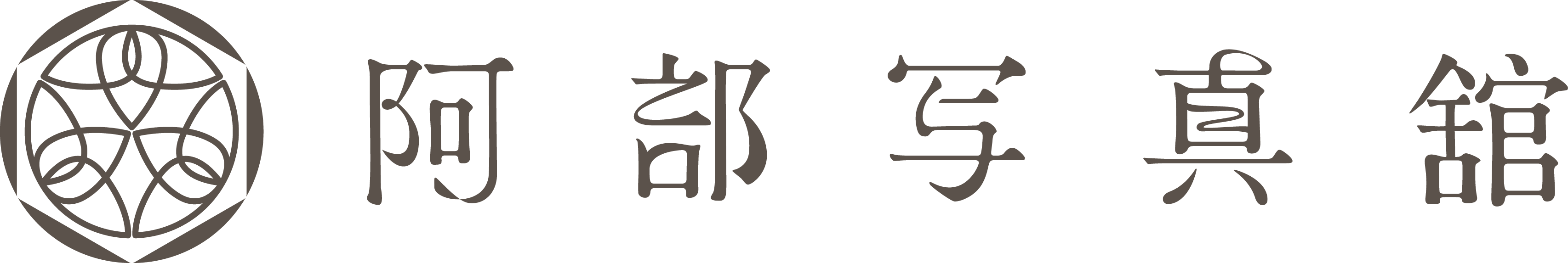丸亀町のファッションブランド”Green”のオリジナルキャップ
"Be Happy"
春の柔らかな日差しが、カフェの窓辺をオレンジ色に染めていた。莉子はいつもの席に座り、温かいカフェラテをゆっくりと啜る。今日は少しだけ勇気を出して、窓の外の景色ではなく、店内の隅に座る男性に意識を向けていた。
彼はいつも一人で、静かに本を読んでいる。整った横顔、時折見せる優しい微笑み。莉子は彼のことを何も知らなかったけれど、その穏やかな雰囲気に惹かれていた。
ある日、いつものように彼が読書に耽っていると、突然、彼の持っていたマグカップが傾き、中身のコーヒーが白いシャツにこぼれてしまった。彼は慌ててハンカチで拭こうとするが、染みは広がるばかり。
莉子は咄嗟に立ち上がり、自分のバッグから予備のハンカチを取り出した。「あの、もしよかったら…」
彼は驚いたように顔を上げ、少し戸惑いながらも「ありがとうございます」と受け取った。
それが、莉子と彼の初めての言葉だった。
それから数日、カフェで顔を合わせるたびに、二人は短い言葉を交わすようになった。彼の名前は健太といい、小説家志望であることを知った。莉子は自分の仕事のこと、好きな本のことなどを話した。
ある雨の日、莉子が傘を持たずにカフェを出ようとしていると、健太が自分の傘を差し出した。「よかったら、これで。」
「でも、健太さんは?」
「僕は少し濡れても大丈夫です。また明日、ここで。」
翌日、莉子がカフェに行くと、健太はいつもの席で微笑んでいた。莉子は昨日のお礼を言い、自分の持っていた小さな焼き菓子を彼に差し出した。
「これ、よかったら。感謝の気持ちです。」
健太は少し照れたようにそれを受け取った。「ありがとうございます。あの…もしよかったら、今度、僕の好きな本について話しませんか?よかったら、ですが。」
莉子の心臓がドキリと跳ねた。「はい、ぜひ。」
その日から、二人の距離はゆっくりと近づいていった。カフェでの会話は弾み、時には一緒に街を散策することもあった。健太の優しい眼差し、莉子の明るい笑顔。お互いの存在が、二人の日常にそっと色を添えていった。
ある夕暮れ、公園のベンチで並んで座っていた。沈む夕日が空を茜色に染め上げている。健太がふと、隣の莉子に視線を向けた。
「莉子さんといると、なんだか心が安らぐんです。飾らない自分でいられるというか…」
莉子は少し赤くなった頬を隠すように、夕焼け空を見上げた。「私も…健太さんといると、とても穏やかな気持ちになります。」
沈黙が二人を包む。それは気まずい沈黙ではなく、心地よい静寂だった。
健太は意を決したように、莉子の方を向いた。「あの…もしよかったら、これからも、もっと色々なことを話しませんか?一緒に、色々な場所へ行ったり…」
莉子は顔を上げ、まっすぐ彼の瞳を見つめた。その瞳には、優しさと少しの緊張が宿っていた。
「はい、お願いします。」
健太の顔が、夕焼けよりも温かい笑顔で輝いた。莉子の心にも、じんわりとした温かい光が灯る。
カフェで偶然始まった二人の物語は、まだ始まったばかりだ。けれど、お互いを想う穏やかな気持ちが、きっとこの先も二人の心を優しく照らしてくれるだろう。
窓から差し込む春の光は、二人の未来を祝福しているようだった。Be Happy。そのシンプルな言葉が、二人の心の中でそっと響いていた。
......................................................................................................以上のショートストーリーは"Gemini"作
何度も言ってきたが、誰でもストーリーを描ける便利ツールのお陰で、かえって個人の創作意欲が失せてしまう。これは"Be Happy"だろうか。この程度のストーリーは3秒かからなかった。AIの革新的技術は ”Don't worry, be happy !” か?
そう思いたいが、自分の中で利用策・打開策が見いだせずにいる。