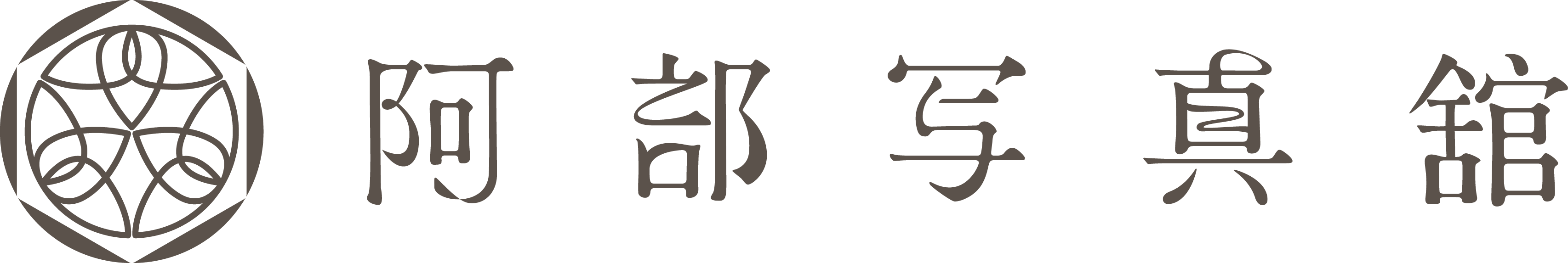表題は檀一雄の句。彼が2年ほど(1970-1972)暮らしたポルトガルのサンタ・クルースで詠まれた。彼はこの地で「火宅の人」を書き上げる。
彼はわざわざ小説を書くため、なぜ地の果てに赴くのか。売れっ子作家の気持ちは素人の僕には理解できないが、自分を追い込まないと書けないテーマでもある。一方で地元民との交流で癒されながら、生活者の視点も保たなければ、作品の推敲中に精神の異常をきたすかもしれない。
「人間とは何か」の問いに真っ向勝負を挑んだ「孤独な勇者」壇一雄の転地生活作家スタイルは、そのまま村上春樹にも受け継がれている。
言葉にする作業とは、極大のエネルギーを必要とする。挑戦者は生活破壊、一家離散などの憂き目にも遭いかねない。破天荒な放浪詩人、破滅型ストーリー・テラーの彼を真似ることは誰にもできまい。
逆説的な物言いだが、言葉にする作業(執筆)に取り組んだりしなければ、もっと「幸せ」に包まれていたのでは。そこに大いなる矛盾を感じる。そして嫉妬も感じる。

リスボンの街角で