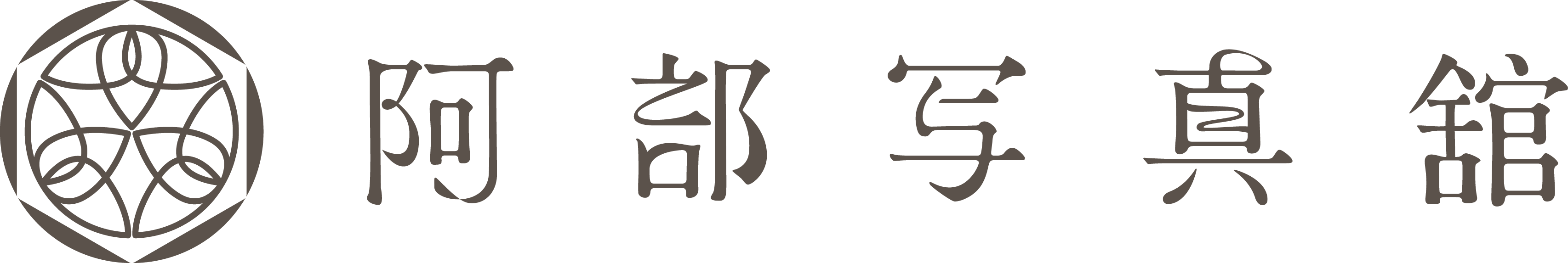父・幸夫と私
父・幸夫が結婚した昭和二十二年は戦後復興に向かう気力がようやく出始めた時代。戦前、一家を支える祖父はたくさんの使用人を雇い、日々充実していた。しかし空襲は残酷だ。一代で築いた店舗も自宅も焼夷弾でなくし、その後は細々とタバコ商を営んだ。
それでも「長男は跡を継ぐ」ことが当然とされる時代。幸夫を高等小学校しか行かせなかった。学業優秀で担任が進学すべしと喜作(私の祖父)に談判したが両親揃ってその進言を頑として受け付けなかった。喜作は競輪場にタバコを運ぶのが日課で、孫の私はよく連れられていった。幸夫は市役所勤務の職を得たが、臨時で県庁に出向していた。後に正式採用される。わずかな月給のほとんどを祖母は巻き上げ、新婚所帯も我慢を強いられた。商家から嫁いだ美津江(幸夫の妻)との新婚生活は想像を超えるほどの二重苦であったろう。幸夫の下に五人の姉弟がいた。その生活全てが父の肩にかかる。一番下の四男は父と二十も齢が離れ、美津江は自身の腹を痛めた息子達と分け隔てなく育てる使命を負った。母は夫を信じた。「辛抱」は最大の美徳。戦争で大敗しながら国民すべてが耐えることを美徳とした時代。あの美しい時代のことだ。もうあの時代に戻ることはできない。