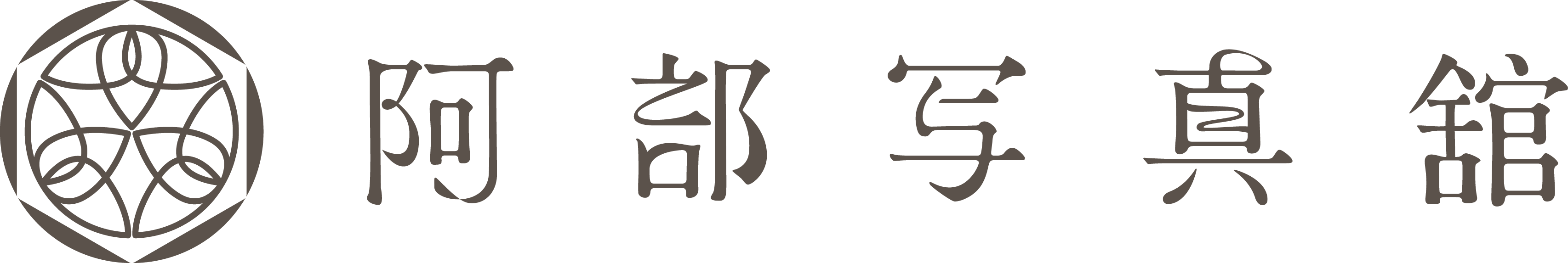いまは故郷から遠く離れて暮らす聡志。JR大垣駅に降り立つ瞬間、特別な開放感に満ちる。駅は南口も拡張されて地方都市にしては意外に整った構えになっている。北口からは長い連絡通路がショッピングセンターまで続く。どこにでもあるメガマートだ。聡志は流れのまま南口に出た。ここから100m先に生家があった。その土地も今はビルに飲み込まれてしまったが。
(いい時間だな)
(こんな時間に大垣に降り立つのは久しぶりだ)
聡志はここを起点に大阪までヒッチハイクした遠いあの頃を思い浮かべた。
(あれはひどい旅だったなあ)
同級生の野田の顔が浮かんだ。ふたり警察に連行され、はたまたヤクザの車に拾われた思い出すだけで笑えてしまう。
携帯のサイドボタンを押して時刻表示を見る。
(もう6時かぁ)
岐阜はまだコートの襟を立てなければ寒いほど。
(寒そうな夕陽だ)
通勤帰りの時間というのに、街角の人陰の少なさにすこし驚いた。退屈な時間を持て余すことは覚悟していたが、今回はなんの予定も入れないまま、新大阪から飛び乗ったのだ。

(大垣駅前から西を望む)
同級生の誰かに会いたい訳でもなく、駅前をぶらつく。こんな時は寿司屋がいい。春魚の旬はまだだろうが、暇そうでそれでいて老舗らしき寿司屋を探した。アーケードの両側を南北つぶさに歩く。そして目星をつけた「寿司辰」の暖簾をくぐる。入り口のショーケースにはロウで出来た寿司のサンプルが並ぶ。ホコリが積もっていた。
(エィ!ラッシャイ)
カウンター越しにいかつい男の声。彼のマメ絞りがかえって顔のデカさを強調している。年の頃は30代とみた。カウンターは10m以上ありそう。カウンターの反しも飾りでなく見事に彫られている。檜のいい香りだ。一番奥にやはり50年配の店主が陣取っていた。大きな目の持ち主だ。客はもう一組二人連れ。県外客と思しき風情。店奥の天井近くには34inchのテレビが吊ってある。客は巨人阪神戦に興じている。地方の寿司屋はどこでもこれがお決まり。もともと客待ちの店主が観るためのものだ。一概に邪道と言ってはいけない。この不況でも店を立派に維持している。
「まずはお飲み物から?」
少しふてくされた顔を明るいトーンでごまかしながらホール担当の店員が近づいてくる。
(お決まりのアルバイト店員だ)
「じゃあビールで」
その間にネタの鮮度を吟味しようと、ショーケースに眼をやる。さすがこちらは新規の客とみて店主は敏感に反応する。
「八海山ありますよ」
「じゃあ後でもらおうか」
店主はデカ顔の従業員と狭いカウンター内で態を入れ替えると、こちらに近づいてくる。
「お造りでいきましょうか」
「うーん! 何か握ってもらおうか」
聡志はこんな時決まって、
「白身なんかある?」
「鳴門鯛なんかどうです?」
(俺は徳島から来てるんだけど)
でも口には出さない。
「じゃぁそれ握って」
「一巻にしましょうか」
「いや二巻で」
聡志は腹が減っていたのだ。主人はこちらの素性をまだ計りかねている風だ。会話の糸口を探している。デカ顔マメ豆絞りが横から会話に割って入ってくる。
「お客さん。通はやっぱ白身ですね」
(弟子なのに余計な口たたくなあ)
そう思いながら勢いよくビールを飲み終わると八海山を燗で頼んだ。食は進み蓮根の煮物をつまんでいると、絶妙のタイミングで、
「トリ貝の身は生きている間透き通ってるんで」
店主はデカ顔に向こうの客を任せると、こちらに意識を向けてきたわけだ。
「トリ貝ってこれですか?」
「ふつうは火を通してネタにするんですがね」
「お客さん生で食べたことあります?」
あまりに見事な透明感と締まった墨色の身に納得。聡志に躊躇はなかった。
「じゃあそれいってみようか」
一口入れると、紛れもなく磯の香りがする。知多半島の香だ。
店主は語り始めた。創業68年で彼は四代目。紡績会社が撤退してから街が沈んだこと。しかし眼前の彼には静かなプライドがあった。謙虚さの中に溢れる職人の自信。食べることが人生のすべて。そう背中で語っているようだった。