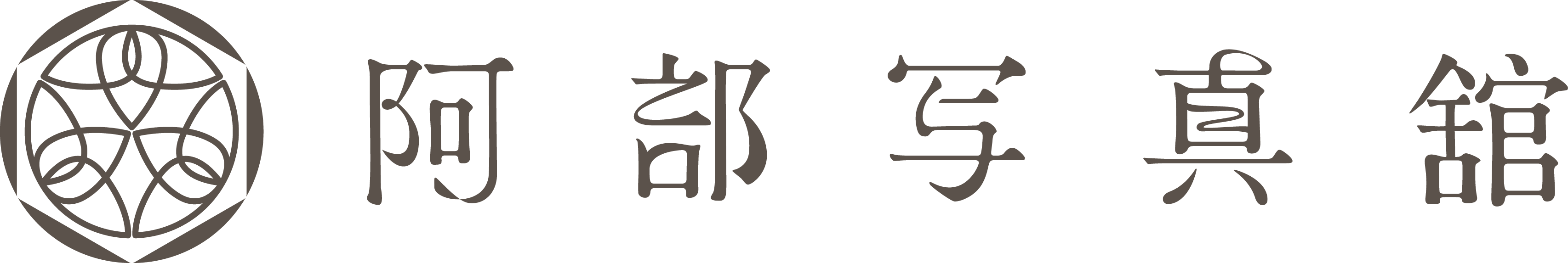しばし退屈しのぎにお付き合いください。退屈なのはどちら?なのか定かでありませんが。

1975年頃の京都市内街頭スナップ
「りっちゃん」
「あーら、二人ともそんなところへ入り込んで仲良しでいいわね」
りっちゃんのお母さんに覗かれて浩史と律子は、急いで身をよじって手許を隠すような素振り。りんご箱をいくつか積み重ねたふたりだけの秘密の場所には、屋根に雨除けのモッコを被せてある。おかげで暗がりになってお母さんからは見えにくい。
二人の様子に安心したのかお母さんは家に戻った。
「きょうは、りっちゃんが先生だよ」
律子は自信満々の素振りで浩史に言い放つ。1歳年上のりっちゃんには当然の立場だ。さっそく浩史に指示を出す。
「どこが痛いんですか? 先生が診てあげますよ」
「さあ、恥ずかしくないよ。出してみて」
少しドキドキはしたが、素直に従う浩史。それを取り出すと、律子は右手でさらに引っ張り出す。左手に用意したピン止めを浩史のものにあてがう。
「ちょっと痛いかな? 心配ないですよ」
そういいながら、律子はピンをその中心部に差し込み始める。浩史は怖くなって腰を引きたかったが、りっちゃんの左手はしっかり握ったまま。痛み少し感じたが浩史は我慢しながら、眺めるしかなかった。
「大人になったら浩くんのこれ、もっと大きくなるかなあ」
「そしたら、りっちゃん、また診てあげるから」
どこか自信満々の彼女はいつも先生役ばかり。一度だけ浩史は診察側に回ることを許された。あれはいつのことだったか、この狭い小屋に四つん這いになったりっちゃん。
「浩史君。恥ずかしいから何か被せてくれる? そう、これ被せて」
そういうと、彼女は上着を脱いで自分からお尻に被せた。
「どこが痛いんですか。先生に言ってくださいよ」
浩史は大胆にりっちゃんのお尻に顔を近づけ、割れ目を指で撫でてみた。浩史は黙々と診察を続ける。
「りっちゃん、キズが二つあるけど、どっちが痛いんですか。先生に言ってくださいね」
これが最初で最後の浩史先生だったかもしれない。
さっきから、少しそわそわしているりっちゃんが言う。
「わたしね、おしっこしてくるからこのまままっててね」
「今度は浩くんが先生の番だから」
(そんなこと言ったってまた僕ばかりいじくり回されるに決まってる)
浩史は恥ずかしくて、そしてそこが痛くなってきたので仕舞おうとして握ってみた。それは今まで見たこともないくらい縮んでしまって、少し先から血が滲んでいる。
怖くなった。浩史はそこからピンを外すと、家に帰るしかなかった。
「僕もおしっこしよ」