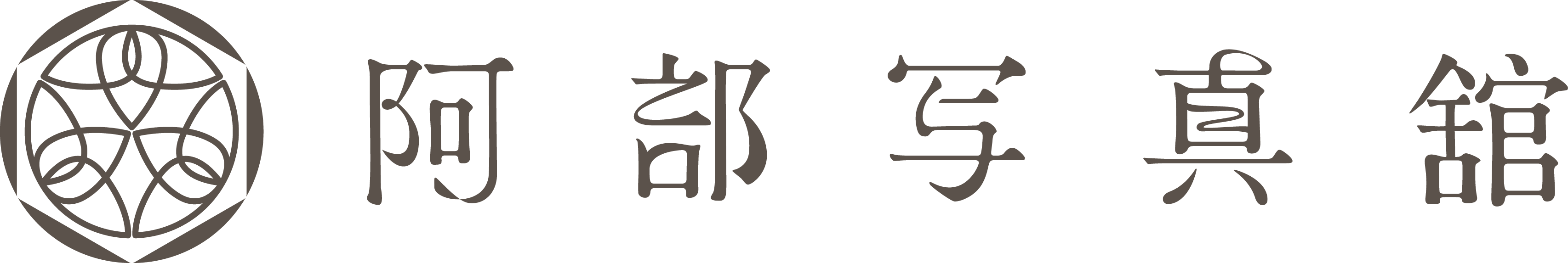歴史的名著紹介です。氏は日本を代表する知識人・言論人でしたが、妻に先立たれて後に、ついには自ら命を絶ってしまった。出版社の担当者が自殺幇助罪で検挙される騒ぎもありました。以下にこの絶筆となった名著の核心部分を抜粋して皆様にご紹介いたします。

(堤防)
第九節「日本人論の数々――概念と雑感」
長く生きているといろいろな書物群を読んだり瞥見したりする。日本論についてもあれこれの記憶があるが、しかし、述者の場合、物事についてのパースペクティブを得ることが主眼であるので、その書物体験はいつも雑駁なものに過ぎなかった。そのことを告白した上でカレンダーイヤーに沿って記憶を整理してみると、次のようなものになる。まず聖徳太子の十七条憲法のことが思い起こされる。しかし述者の覚えているのはその第一条に「和を以て貴しと為す」とあリ、第十四条に「群卿百寮、嫉み妬むことあるなかれ」とあることくらいだ。いや、そのほかに「群卿百寮、礼を以て本とせよ」という(いわば仏需習合の)道徳論もあったはずだ。
いずれにせよ、蘇我氏が物部氏を滅したあとのことであるから「和」を大事にせよといったのは、この国にあってもいかに争い事が絶えないかということの逆の表現とみるべきだし、「嫉妬」諦めて居るのも、日本人もまた往時から嫉妬深いかということの証言だとみるべきだ。なぜそんな事を確認するかというと、「日本人は平和で互いに仲のよい民だ」という俗説が今に至るも絶えたいからである.ついでに付け加えておくと「礼」を大事だとしたのは、またほかの条で’怒リを抑えよ」といっているはずなのは、すでにこの国に文化の混沌が始まっていたことを明文化したものといえよう。
その後「大化の改新」の内乱や白村江の敗北や壬申の乱などが続いたのであってみれば、中国のいわゆる律令体制の導入にもさまざまな混乱が伴なった様子がみてとれる。また仏教の導入にしても、奈良時代にすでに「本地垂迹説」にもとづいて、旧来の日本流アニミズムに発する神々を仏によって救済される下位・神々とみなすという「神仏習合」に取り込まれたことを思うと、日本文化の雑種性は歴然としていると言ってよい。
八世紀の初めに記された古事記をどう位置づけるべきか、その中国を範とする「からごころ」の姿勢に立つ国造の物語は、万世一系説の始まりという点を強調すべきではなく、日本人がストーリーとして歴史を語るのに巧みであったことを確認しておくべきであろう。その書物への綿密な解釈が行われはじめたのは江戸期に入ってからのことではあるが、国家がいかにして形成されたかについての三説つまり他民族の支配説、優越階級の支配説そして神話の共有説の三つのうち、日本人の歴史観にあって三番目の神話説が最も有力であることを証していると迁者には思われた会、今上陛下の生前退位に関しその是非や法律改正・当否がかまびすしく論じられているが、そこに欠けているのは、何ほどのリアリティをもったミスが言語的動物としての人間の集団にあって最も深い底層にあるということが確認されていないということである。たとえば男系天皇が百二十五代続いたことは事実かどうか、ということばかりが論議の的となっている始未である。古事記におけるいわゆる天孫降臨説などは、外国からの価値や権力の導入を神話化したものであって、それを神話として受け入れる度量がありさえすれば自分らの歴史を事実というよりも事実をめぐる物語とみなすことができるはずなのである。なお「やまとごころ」に立つものとしての万葉集が.日本人の自然にして健康な感情を歌い上げていることは誰もが知っている。
平安期に入って日本は中国大陸との交流を断ちつつ、空海の発明による平仮名に如実に見られたように、独自の政治および文化の圏域を形成しはじめた。その方向にあって着目すべきはいうまでもなく源氏物語であろう。それへの徹底した解釈が施されたのも江戸期に入ってからのことではあるが、日本人が自己の他者との関係のなかで展開される、感情・情緒・情念の運動といったものに、いかに敏感であるか。それを示しているのが源氏物語である。述者はそれを読み通したことすらないのだが、そこに人間の感性というものの自律的な動きに、それのいささかならぬ手弱女(たおやめ)ぶりに辟易したがらも、人間の言語活動が論理のみならず感情によって、というより感情を細やかに仕分けする論理C・レヴィニストロースの言った分割主義一によって、展開されるものだということがはっきりと示されている。しかし、それを日本人の心性や行動の目立った傾きとみなすことは可能であろうが、日本人にのみ特殊なことではあるまい。中国大陸や朝鮮半島との文化交流が少なくなった時期、つまり日本列島が一個のコスモスとして自立した時期に論理の前堤や組立てに感性というものが濃密につきまとうということがその書によって示された。と述者は受け取っている。
平安末期から鎌倉期において日本人論として特筆されるべきは、まず鴨長明の方丈記や吉田兼好の徒然草におけるいわば人性論と社会論における物事の深奥を深く諦かにするという意味での諦念であろう。両者は、源平合戦と南北朝合戦というふうに時期を隔てているが。この世の無情の中で生きてそして死ぬにはぃかなる境地に立つしかないかを深く考え抜いた作品といってよい。そして両者とも無常の中での自然さ探して不動の感覚や諧謔の精神に近づいていったのだと思われる。
だが日本人の心により深く残っているのは、それ以上に平家物語における敗比の美学によって語られる宿命論理的な歴史観であり、そして鎌倉新仏教の登場ではないのか。前者における諸行無常と盛者必衰のことわりは、それが徳川幕府であれ大日本帝国であれ、その後日本人が何度も耳にすることとなった歴史の弔鐘なのである。
浄土宗および浄土真宗は阿弥陀仏をいわばー神として念仏による人間的苦悩の救済を訴え、法然の俢行論が親鸞の信心論となることを通じて、たとえば悪人正機などが唱えられつつ、それは農民をはじめとする一般庶民の心にまで深く食い入っていった。道元による曹洞宗は、主として只管打座とを要求した。それが主に武士階級によって受け入れられ、いわゆる武士道なるものの意識に根元を与えることとなった。それと同時に。貴人に侍(さぶらう)う者たちに、その代償として、土地の支配を任せられるという安堵の制度が、つまり契約観念が定着していったのである。
話を宗教のことに戻すと、少し遅れて日蓮は立正安国を唱え、念仏や座弾といつた行為なしの意識などは無効だとして、元寇襲来の直前にあって、国民の政治意識と宗教意識を合体させるべく法華経を中心において宗教を実践の場へと連れ出した。日蓮宗はその後、近代に至ってもなお、様々に枝分かれしながら、政治と宗教のかかわりに関与することとなったのである。
もちろん平安期に始まった空海の真言宗も最澄の始めた天台宗も、それぞれ密教的お祭儀を中心にして…人間のスピッツチュアリティつまり霊性を示さんとする運動として…健在でありつづけた。ちなみに述者は、神道のであれ奈良平安の旧仏教のであれ鎌倉。新仏教のであれ人間精神の霊性なるものこ多大の関心を持つものの、それはあくまで抽象のレベルのことであって、具体のレベルでは-嘘いつわリの少ない経験論として描写されるべきだと思う。ともかく以上を合わせる四種類の宗教形態はわかりやすく言えば、親鸞は社会的伝達に努め、日蓮は価値意識の政治的表現に、道元はその尺度文化的追求.そして旧仏教はその蓄積…歴史的経験を重んじた、と分類できよう。追加しておくと一遍の始めた時宗は、いわば踊る宗教として宗教意識を身体次元にまで引き降ろしたものであるから、言葉による説明を超えた次元にまで入り込んでしまったといえる。
いずれにせよこの時期に宗教的な意識と行動のありうべき基本型のすべてが開示されたのである。
その後、室町足利期と戦国期の内粉と内乱が長きに及んだ結果、みずからのナショナル・アイデンティティを問う声すらがこの列島から失せていった。、、や、そうであればこそ、佐々木道誉らの「婆娑羅」の精神が、いわば死活の戦いの前での芝居・演出が、日本人入想像力を「幽玄」の感覚を中心にして開拓していった。それは生と死過去と現在の間、いわば限界状況にある武さたちの人間精神の内面界に深く沈潜してみせたのであり、いわば日本人における実存の心理も表現したと言えなくもない。なお雪舟の水墨画や干利休の茶の湯に日本人の美意識を探ることも可能なのではあろうが、その美意識が日本の社会制度や国家意識とどう繋がっていくのか、述者には日本における繊細の精神という以上のことをいう能力がない。
その末期にF・ザビエルの運び込んだキリスト教がとくにバライソ=天国の思想をこの列島に注入しようとした。しかし、ジェスイット派のユニバーサリズムのうちにスペインやポルトガルの覇権意志が張り合わされていることを見抜いた秀吉や家康によって、その西洋の宗教は禁圧された。私見ではそうするのが日本にとって必要であり有益ですらあったと思われるが、しかしそれと同時に国内では、宗教への政治介入のせいで、宗教のすべてが単なる儀礼へと堕ちていったことを見逃すわけにはいくまい。それのみならず信仰なるものが単なる個人心理の次元に押し込められ、信相が絶対・超越・崇高の次元を仰ぎ見る信仰願望集団のカビナントとして成立する。という宗教と社会とのかかわりもまた見過しされることになった。特に問題であつたと思われるのが、その盟約において展開されるはずのいわばカテキズム=神学がこの国で癸達せず、理と切り離された心の問題の中に信仰は封じ込められた、という経緯ではなかろうか。
そうであればこそ、江戸前期に伊藤仁斎が、古義学と称して儒学の古典を新たに解釈し直しつつ、朱子学を批判して、人々の生の次元における感情の深さや道徳の重みを重視せよと「仁」の思想を唱導したのである。江戸幕府は林羅山などによって「礼学」を単なる儀礼にまで縮めた朱子学をいわば官学として採用した。そのことに対する批判が、仁斎によって始められたということである。
この流れは中江藤樹や熊澤蕃山などによる陽明学と軌を一にしているということができる。つまり知行合一の見地から、朱子学のような空理に滑るのではなく、人間の生の時と処と位に応じて具体的に実践と結びつくような、人間社会への解釈が陽明学によって切り開かれたのである。この流れは幕末における大塩平八郎の乱や幕末の志さたちの討幕の思想と行動にまで連なっていったと見てよいだろう。それとはかたりに色調を異にする流れとして、荻生側来が古文辞学を立ち上げつつ、ということは古代中国における中庸という形での矛盾・処理を言し学に担わせながら幕府や藩の運営に関に合理的で現実的な態度を取った。ということも記憶されるべきである。たとえば彼は、あの有名な赤穂浪士討入事件に関し、いわば法治と徳治をバランスさせて、浪士たちへの切腹といういわば名誉付与を伴う制裁を遂行したのである。その封建における契約観念の発達は合理的に則るものであり、江戸期においてすでに現実に対する合理的な対策という意味での近代主義の思想ガ育まれていたということができる。各藩の運営においても、同様のことが起こっていたことは推測に難くない。たとえば米沢藩の上杉鷹山がそうであったし。幕末においていわば守募開国の立場をとった小栗上野介らの冾理的開明派もその流れに属するといえよう。

(東祖谷山村)
これとは別の流れとして国学が、日本国の人間観と歴史観をあらためて問い直すものとして、契沖の仮名遣研究を嚆矢に、賀茂真淵の万葉集をめぐる古道説と称される解釈は日本人の自然な感情表現に焦点を置くものであり、その方向は本居宣長によっていっそう深められた。あっさりいえば、古事記研究は日本独自の歴史観・打ち立てるためのものであり、また源氏物語研究は宣長。いった「もののあはれをしる」ことという言葉に代表されるようにつまり人間が自然や他者にかかわるときに、宿命的に訪れる「あはれ」という心情からの逃れ難さ、それを知ることこそガ人間の死生観のあるべき姿と宣明されたわけだ。それは外来の「からごころ」から脱して日本に本来の「やまとごころ」を取り戻そうとする営為であった。
述者は山崎闇斎のような垂加神道における神秘主義や江戸末期における平田篤胤の古道神道の情念論には疎遠な気持ちしか持ちえない。とはいえ国学全般に通じる歴史的に形成され来ったアイデンティティを求めんとしたその姿勢は、西洋諸列強の覇権が徐々に日本列島に近づいてきたのが江戸時代であったことを考えると、当然起こるべくして起こったものと見ざるを得ない。
そのほかにも石田梅岩の石門神学に代表されるように、一般庶民のレベルでの日本人の生活者としての在り方つまり実学が論じられてきたことも見逃すわけにはいかない。その流れは江戸中期の安藤昌益による人間と自然の調和の思想や山片蟠桃の唯物論的な世界観へと発展し、さらに江戸中期の二宮尊徳による農耕生活の知恵へと続いていった。
さらに文芸の方面にあって松尾芭蕉の俳諧は、いわば世俗を旅しつつ脱俗を表現するものとしての「かるみ」の精神を彫琢し日本人の暮らしのただなかの言葉の芸術を持ち込んだのであった。
なお、平和の続いた徳川の中期に入る頃、山本常朝が『葉隠』を書き、武士道の何たるかを論じた。それは武士道が廃れ行くことへの抵抗に他ならないが、それの残した二つの科白、つまり「武士道というは死ぬことと見つけたり」というのと「人間一生まことに僅かのことhたのであった。--------なお述者としては「最も好きなことは死ぬ理由を見つけることだ」とみなせば、其の矛盾はすぐ解けると考えている------。そして水戸の会沢正志斎や長州の吉田松陰の「尊皇思想」は、日本の「国体の名文」を天皇に求めつつ、それに伴う攘夷か開国化については紆余曲折を経たとはいえ、それまた武士道と陽明学の両系譜に立つ実践思想であったといって差し支えない。
なお佐久間象山を始めとするいわゆる蘭学としての実学は、その和魂洋才の標語は人ロに膾炙したとはいえ、日本人論としてみるべきものがあるとは思われない。要するに蘭学は兵学をはじめとする狭い意味での実用の学にとどまったのであって、洋才に馴れ親しめば和魂が消えうせて洋魂に取って代わられる、という当然の心理学および社会学について蘭学派は無頓着だったのである。
いや,この無頓着が近代日本を広く覆うことになったとし、って過言でなくその結果、宗教観や歴史観にもとづく日本人論が次第に姿を消していった。つまり和魂洋才の看板はいまもなお日本国家から取り外されてはいないのである。技術大国になりおおせた現代日本が。内部の文化的混迷や外部からの政治的軍事的圧力にさらされるとき、多くの日本人は自分らを安堵させるべく、和魂洋オで日本の国柄を守ろうと言いつづけているのである。
かつての朱子学の性即理…この世・事物・法則性が人間の生をも貫いているとする見方も単純化の行き過ぎだが、「心魂と才術」の二分法も無理の多い見方だ。
以上、江戸期の日本人論を振り返れば、まさしく群盲象キ無でるが如く日本人の輪郭・それぞれー側面にのみ光を当てたものが群居していたと言ってよいのではないか。その挙げ句、明治維新の「維」(これまた)は温故知新と同意であるということすら忘れられて、いわゆる文明開化の「御一新」が始まったのだ。それにつれ薩長に対する会津藩の抵抗や、その後起こった不平武士の反乱と呼ばれている西南の役などは、維新における単なる逸脱のエピソードとして語り継がれるにすぎなくなった。そうしたリアクションの経緯にこそ日本人らしさを守ろうとする精神が込められていたのではないか、という問いすら忘れ去られたのである。
詳しく見ると明治維新における開化論の流れに遭っても、すでにみたように福沢諭吉や中江兆民に顕著にみられるように、思想としては儒学の道徳論が継承されているし、それには江戸期における武士道すらが引きずられていたとみてよいだろう。同じ傾きが岡倉天心による東洋精神の弁護論にもみられるといってよい。明治大帝の「五箇条のご誓文」における「万機公論に決すべし」の要請は、藩閥や政党の私論はびこること少なくなかったとはいえ、武士道の残影のおかげで、日清・日露の戦を成し遂げつつ、かろうじて守られていたといえるだろう。その端的な例を挙げるとキリスト教に改宗した新渡戸稲造と内村鑑三すらが明治30年前後、前者は武士道において後者は代表的日本人において、武士道を日本人の道徳論として打ち出している。-------いや、両名が自分らの信仰であるはずのキリスト教を持ち出さずに論を展開したのは、日本人がいかに形而下の事柄に関心が深いかの逆証だ、とみるべきかもしれない。しかし新渡戸自身がその所の序文で認めているように、明治32年に武士道の方向で道徳おいて武士道はほとんど消していたのである。明治初期から開化に揺れる日本人の不安心理は樋口一葉などによって鋭く表現されており、その流れの果てで、夏目漱石はその最晩年にあって、「現代日本の開化」という講演で、日本の近代化が外発的であって内発的でないことに警鐘を鳴らしていた。森鴎外も日本の歴史という土壌に自らの物語を植えようとしていた。明治、大正、昭和の近代を総じていえば、その日本人の「百家争鳴」というか、「様々なる意匠」というかいろいろな思想実験が入れ代わり立ち代わり現れたに過ぎない。自然主義も試みられたし浪漫主義も求められた。大正期にはまず民本主義が唱えられ、教養主義の看板の下に西洋近代の新しい動きが紹介され、それに応じて教養ある人格が理想とされた。また教養主維持末期からは社会主義も提起され、感覚主義も実験された。そして日本浪漫主義が唱えられ、またしても古事記や万葉集などから日本の魂が拾い出されようとした。そしてもちろん日本改造のためのウルトラナショナリズムも試みられ、また日本人の根源的な形を「無の思想」に求め、西洋の合理主義を何とか乗り越えようとする京都学派の活躍も見られた。それらを通じていえるのは、一方で個人心理の内面にみずからを昇華る。という統合失調的な動きであったと言えよう。
あえて一言でまとめれば、ハイブリディティゆえのコンプリヘンシヴ衤スによって特徴づけられる日本文化は、それらを統合するプリンシパルへ向けての思想と討論が不足するなら分解するほかない、という危険につねにさらされてきたのである。そしてその危険が現実のものとなれば、茸ヌも「刺激的と流通カ」の高い新奇なアイデアが社会を席捲することになるのだ。たとえば自由民権運動などは、その渦中におかれた兆民が自認しているように「ゴロッキの所業」とみなされても致し方あるまい。
少し遡るが、1880年代の中頃になるか「鹿鳴館時代」と呼ばれる欧化主義は我が国の恥辱といえようがそれを何とか押さえるべく、E・フェノロサによって日本文化。優秀性とその自立性が暄伝され、その日本回帰の流れの中で「歴史小説」が手掛けられ、次に民俗学が始められた。しかしそれとて近代日本に残存する慣習に対する過大評価やスピリチュアルな想像力の両方向に分解していった。それはまさに日本と西洋との葛藤の錯乱せる紋様なのであった。
自己の歴史の包括的な理解に失敗した日本の近代の中で一つだけ変わらなかったのは、尊皇の礼儀作法のみであったと言えなくもない。「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」の建前だけは変わらずに続いたのである。日露戦争の大奮戦は、西洋化における成功報酬として関税自主権の回復をもたらしてくれはした。しかしそれは決して日本の自立のための確かな礎石になるようなものではなかった。天皇の前で演じられた催しは、デモクラシーとミリタリズムの対抗という単純きわまる筋書きの政治劇へと収斂していった、とえば言い過ぎではあろうが、政治・社会・文化が日本的なるものを分解させておいて、天皇・皇室が存続にあられるから日本は大丈夫、というのはあまりに浅薄な日本論だということは確かである。述者は大東亜戦争を世界史の必然としておおよそ肯定するのみならず、戦前。戦後への国民精神における優越を主張するものであるが、日本的なるものを捨てる方向に少しずつのめりこんでいったのが大日本帝国、そういうものが滅亡するのもまた宿命的な成り行きであったと言わざるを得ない。つまり「文明の紊乱」において戦前と戦後は連続しているということである。
そして戦後が始まり、民主制と産業制が狂瀾怒濤となって脹らみ続け荒れまくる次第となった。今もなお日本の底力について喋々と肯定する声が小さくないが、述者のみるところ。日本の文化は投票と金銭の氾濫のため底を割ったのである。以上が後段で少々の追加的な説明をするものの、述者の日本論に関するとりあえずの素描である。なお、この節を整理するに当たり、「日本人とは、そも何者ぞ」しておける評伝作家の澤村修治氏および文芸批評家の浜崎洋介氏との座談が大いに役立った。両氏に心から感謝申し上げる。