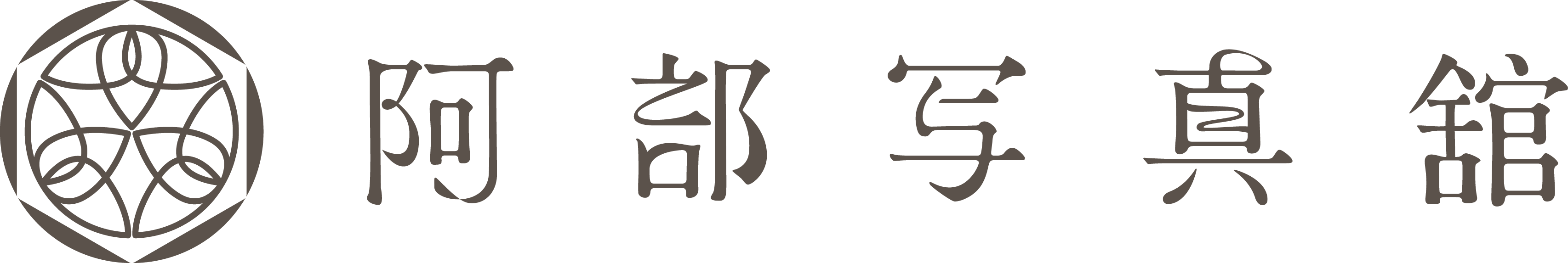お恥ずかしながら、拙著のほんの一部をここでご紹介します。昭和初期を舞台にした小説です。七つの単元に分かれており、その中から二つ目のタイトル「天窓の明かり」の一部分です。

父と祖父のローライフレックス
「天窓の明かり」
倫太郎の工場は薄暗く、柱や壁は積年の黒ずみも手伝ってか、とても写真になる場所ではなかった。乾板の撮影感度は曖昧なまま、ただ勘に頼って撮影してきた義定にも見当がつかなかった。義定は急に思いついたように、
「もっと工場の奥を見せてくれまへんで」
倫太郎は、寒さをしのぐように無意識に袖の中で腕組みをする。深く織り込まれた額の皺に裸電球の光が当たった。
「そやなあ」
「こんな天気やし、外では写せんわなあ。工場の奥は天窓の明かり取りがあるけんど」
いまどきの工場には珍しく、その天窓は北向きに一軒分も設えられていた。あいにく雪は少し積もっていたが、邸内の隅々まで光は届いている。時折ガラスに滴り落ちる雨音が工場にも届く。
(あとは補助光さえあればいける)
そう判断するが早いか義定は撮影の準備を始めた。壁には掻き集めた晒し木綿三反を幾重にも貼りこみ、光をなんとか部屋の隅々まで回そうと考えた。今回の撮影は最近覚えた紙焼き時に赤血塩で明部を減力すればいい。当然この撮影原板は増感する必要もあるだろう。柔らかな女性の肌を原板に再現するためには、現像液の希釈度を変え、明暗比を抑える試験もしようと考えていた。現像時の硬軟調整が仕上がりを決めるはずだから、何枚か写しておかぬと失敗もでる。そう思った。義定は一つのポーズに五枚すべてを投入するつもりになった。
(露出は分からんがやるしかない)
いつも臆せずぎりぎりの挑戦を仕掛けるのが彼の流儀だが、きょうはなぜか慎重になっていた。
(横顔も写そう)
さて、五枚の乾板をどう使うか。大きな賭けだ。ましてや光の届かない冬の室内での撮影は無謀とも言えた。額の汗をぬぐう間もなく彼は準備に精魂を込めた。
世津が京都へ奉公に出るといえば、もう彼女は戻れぬ人とあきらめるしかなかった義定だが、いつかは打ち明けようと一度は決意していた。
(世津との別れ際を写真にしておこう)
(しかしこれが最後かも知れん)
(徳島へ帰って写真場を開こう。わしはそう決めたんじゃ)
女に惑わされて我を見失う彼ではなかった。
(今することは写真の腕を上げるだけや)
だが義定の世津に対する思いは揺れていた。現状を思うと無理な事は承知している。写真と嫁の両方を望むことは、自分でも許せない。そういう男だ。しかしこのまま丹後で写場を開くか、徳島で開業するのか。両方ともに自信はあった。二つに一つ。何かを得れば別の何かを失うのが道理。ここは分別のしどころ。自分は今まで一度も迷わなかったではないか。
世津を奉公に出すと倫太郎から聞きつけたのが十日前、きょう撮影しようと思い始めるまで義定にしばらくの時があった。おかげで吹っ切れた自分が今ここにある。吹雪のなかこうして写真機を持ち込んできたのではないか。倫太郎も義定の気持ちを推し量っているのだろうか。彼にとっての最後の手段は写真機を構えることだ。写真機の後ろに立てば自分は素直で冷静になれると。きっと何かが見えてくる。
写真機の据付け場所も決まり、よく磨かれた桜木の組立写真機を木製三脚座に乗せ始めた。――本当は仏蘭西製のスチール三脚が欲しいのだが、高価でまだ手が出せない。義定はできるだけ簡素な背景を選ぼうと、あえて暗がりの一隅の黒をそのまま使うことにした。しかし漆黒の背景を温黒調の紙焼きに仕上げる技は、まだない。いつか本業の写真師に弟子入りして、その技術を学ばねばならない。調色技術は長期保存を使命とする写真師の必須科目。良い紙焼きを作るための赤血塩の漂白も、微妙なさじ加減ひとつで破綻する可能性がある。技術的にもきょうは一つの賭けだ。補助光の配置もよく観察しないと、ありえない影を作ってしまう。気持ちは奮い立ってきた。
しばらくして奥から倫太郎が世津を伴って現れた。彼女は見事な藍色の紬をまとっていた。彼女の背筋は伸び、気品に満ちている。摺り足で歩くときの絹擦れの音が心地よく、合わせた帯も調和している。
「似合う帯がのうてなあ」
「定やんくれはった帯はな、もったいのうて。これ母親の形見の帯にしたんじゃ」
結局いま世津がしている帯は倫太郎が納戸から見立ててきたのだ。義定が用意した帯は義定渾身の選択と言いたいのであるが、行商先の農家から譲ってもらったもの。新調をためらったのは、帯がそんなに高額なものと知らず、準備も間に合いかねた。きょう倫太郎の選択眼に義定の帯は叶わなかったわけだ。さすが着物を扱ってきた倫太郎の確かな目。薄紺色の紬に砥粉色の帯がよく映えた。誰が見ても息を飲むだろう。義定にはここまでの組み合わせを考える余裕もなかった。倫太郎は決して義定の好意を否定しているのでない。義定は着物と帯の組み合わせまで学ぶことが出来ていないことを思い知った。いや写真という白黒の世界しか理解できず、その感覚で帯を選択しただけかもしれない。
普段から世津は美しく髪を束ねている。義定が来るとわかると普段使うことのなかった椿油で、その黒髪をいっそう際だたせてくれていた。この辺りでは珍しく、小顔で長い首に端整な顔立ちをのせ、大きな瞳が印象的であった。時折彼女が振り向きざまに見せる、見射るような蠱惑(こわく)的な目配り。世津が居間と台所を行き交う際に必ずと言ってよいほど見せる、あの振り返りの目線。義定を釘付けにしてしまう。心を寄せていたのは義定だけではあるまい。
仕上がった世津の姿を眼前にして、彼女を褒める言葉が見つからない。彼女も久しぶりの笑顔だろうか。邪心を吹っ切るためにも、ここは撮影に集中するのみだ。
「この帯はなあ。世津の母親の箪笥から拝借した」
そう語る倫太郎にも格別の思いがあったのだろう。義定は眼前で気恥ずかしさを垣間見せる世津を、衝動的に抱きしめたくなった。彼女は健気に動かず会話もなく、工場は静まり返っている。写真機の前に座る彼女が、手の届かぬ所へ行ってしまうと思うと、その動揺は尋常でない。もし京都の旦那衆に見初められでもしたら。成就することのない恋と諦めることもまだ許せない自分がいる。
我に返った義定は撮影に集中した。空も少し明るくなる気配だ。天窓に積もった雪が溶け始めている。打ちつける雨音。このシャッターに思いを込めることしかない。
「倫太郎さん。少し座敷で待っとってくださいな」
「世津さんも緊張するけん」
義定にとってずっと願っていた大切な時間に、たとえ親でも踏み込まれたくはなかった。倫太郎は、何か手伝うことはないかと言い残し座敷に消えた。
天窓に照らされた世津の髪は神々しく輪郭光線に浮かび上がっていた。意外に細い世津の手足を見て、義定は竹久夢二の絵をまねようとした。〈黒船屋の女〉に憧れていた。その絵は大衆の誰もが評価しており、義定の憧れであり目標にもなっている。画壇からはこっぴどい言われ方をしている作者夢二(ゆめじ)だが、写真の勃興期に遭った画家たちは追い詰められているわけで、こと肖像画に関して、新しい印刷媒体に載った夢二の絵画を画壇は否定することで、我が身を守ろうとしているのだ。義定はそんなことを思い巡らせながら、きょうこの写真の主題を昇華させていく。

二代目
正面に彼女を向けながら座らせると、足は斜めに流し、上体は少し左にひねらせた。闇に浮かび上がる体の線をくまなく写し込みたかったのかもしれない。天窓の光線はしっかりと藍色の着衣を背景から分離させている。さらに世津の正面の顔と義定の気に入っている彼女の横顔を狙う。ソルントン・シャッターをコッキングする。冠布を肩にかけるとピントグラスに顔を寄せ、一度シャッターを切ってみる。
(十秒はかかるな)
露光時間を決めるには勇気がいる。勘が試される場面だ。後処理での救済はできないわけで、経験上こんな時は段階露出するしかない。
静まり返った工場の一隅。またベタつく雪が天窓をたたき始める。
(早く写さねば)
焦り始める。心配なのか義定は写真機を冠布で覆い、二度目のシャッターを落としてみる。するとレンズ越しに一瞬対象が浮かび上がる。その入ってくる明るさと、おおよその経験からシャッター速度を導き出すことができるほどに義定は腕を上げていた。頼れるものは経験のみだ。ただし違うレンズではそれも通用しないが。
「こんなきれいな光は初めてや」
しかし肉眼の暗順応はこんな時に災いするもの。勘も狂う。ひとり何かつぶやきながら、暗部を補うために写真機の後ろに集めた電灯を一つ、二つと灯(つ)け始めた。
(補助の光を使いすぎると空気感を壊すわな)
天井に釣り下がる電球を一つ消した。天窓から降りてくる外光が見極められないと思った。再び義定はピントグラスを覗き込み、浮かび上がる天地逆の像にようやく決心がついた。
(よし、これでいける)
「世津さん、写真ができたら必ず京都に届けますで」
いつも受け身の世津は寒さも忘れて大きな瞳を細めながら頷き笑った。
「ハイ! って言うたら、まばたき辛抱やで 」
「十数える間、動いたらあかんで」
「まばたき辛抱やで」
そう話しかけながら再びソルントン・シャッターをコッキングした。いつシャッターを落とすかだ。義定は世津の心持ち切ない心情を世津の深層に見た。もっと明るい表情などと期待を投げかけることはやめておく。このままでそっと写せばいい。注文をつけることで被写体に入り込んではいけない。彼女の心の叫びを捉えるために。
早くに母親と死に別れ、父の面倒から、弟の学資の心配までが彼女一身にかかっていた。倫太郎は、そんな世津の気持ちを素直に受け止めず、近隣の漁師仲間との酒でごまかし通してきたような男だ。
二枚目の写真を撮ろうとして、間を置く。一つだけ気にかかったのが、手の表情。自然な仕草の中に美しい瞬間があると信じていた義定は、無理に形を整えようとはしなかった。どんなに撮影者が形を整えようとしてもどうしても不自然さは拭えない。世津の手は少しささくれ立って意外に大きかった。どう扱うか迷った。
(手は原板修整やな)
赤みを帯びたその手は、冷たい水仕事と機織りの下働きに駆り出される職人の手そのものであろうか。結局その手は少し陰の中に置くことにした。絹糸の持つ光沢を大切にするためには、どうしても安全な光を求めてしまうが、きょうは天窓の光が主であり、補助光も最小限に抑えたかった。しかし下から仰ぐように当てた二個の電球が、木綿の白生地に跳ね返り余分な陰をつけることはなかった。また天窓の青い光と、電球の赤い光は、視覚だけに頼るとその強弱はだまされてしまう。電球が放つ光を和らげてみようかと、義定は電球の前に直接光が当たらぬよう行灯をかぶせてみた。これで電球の光も和らぎ目に馴染んだ。
義定は二枚目の写真に踏み切れない迷いを紛らわすためか、乾板をセットしないまま、ふたたび空シャッターを切った。(カシャッ!)というより、(パサッ!)。
乾いた音が凍てついた工場にそんな音を響かせる。普段なら寒いとシャッターの可動部分のオイルが粘る。きょうは不思議とそんな粘り気のある音がしない。ソルントン・シャッターの調子を確かめると、シャッターを開け直し、くどいほど慎重にピント合わせをし直した。やはりもう一度ピントグラス越しに世津の姿を確認しないと落ち着かず、まだ露出に迷いもあったのだろう。工場は全体が暗くピントグラスを覆う冠布が必要もないほど世津の姿が浮かび上がっている。程良く瞳と顎の下も照らされ、絶妙な明暗比をとることができている。義定は世津に声を掛けることも忘れ、静かに乾板を装填。気合いを込めてシャッターを切った。
その間、世津は微動だにしなかった。相手の息づかいまでが聞こえるほどの静寂の中、世津は息を吐く時にいくぶん目が開くようだ。今まで気づかなかった発見だ。どれくらいの時間を世津といっしょに過ごしたのだろう。彼女の吐く息も白く写り込んでいるのだろうか。現像してみないと分からなかったが、不安などなく、義定にとっては緊張の中にも快感を伴う時間を過ごせたことに感謝した。この瞬間こそ七年間の結実。この場に心を置くと何かが見えてくる。
段階露出を経てあっという間に五枚の乾板がなくなっている。凍てついた工場の片隅で、義定は呟いた。
「こんなに汗を掻きながら写したこと、ないのお」
額の汗を拭おうともせず、義定はしばしの充実感に浸っている。準備に一時間もかけた甲斐あって緊張の時間は意外に手際よく終わりを告げた。
「義定さん。ありがとうございました」
世津の笑顔で我に返った義定。満足といくぶんの不安と自信が入り混じった笑顔を返した。
「世っちゃん。達者でな」
「また京都へ逢いに行くけんな」
互いの気持ちに何かの変化を感じた。それは義定の満足感が世津に伝わったからだろう。二人の意識は見えないところでつながった。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
もし全部読んでみたいという方はこちら ↓ で販売しております。Kindle版。アマゾン・プライム会員は無料です。